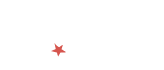★初戦で出た“柔軟性”という課題、予想以上のオマーンに対する打開策は/日本代表コラム

Getty Images
恐れていたことが起きてしまったという表現が正しいだろうか。来年11月に行われるカタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選が2日からスタートした。
恐れていたことが起きてしまったという表現が正しいだろうか。来年11月に行われるカタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選が2日からスタートした。
W杯本大会への切符は各グループ2枚。上位2カ国に与えられ、3位チームは4次予選と大陸間プレーオフを勝ち抜かなければ本大会には出場できない。
2016年9月1日。日本代表はロシアW杯アジア最終予選の初戦で、UAE代表に埼玉スタジアム2002で1-2で敗れた。
この悪夢を忘れた者はいなかったはずだが、5年後に再び同じ事態に。心のどこか片隅で恐れていた結果となってしまった。
◆明らかなコンディションの差
日本が敗れた要因は多くあるだろう。森保一監督、キャプテンの吉田麻也も試合後に口にした通り、「言い訳にはしない」と語ったが、事実としてコンディションには大きな差があったことは否めない。
オマーンはこの日本戦に向けて1カ月に渡り、セルビアで合宿を敢行。チームとしての成熟度、コンビネーション、そして日本への対策は万全だった。
ブランコ・イバンコビッチ監督が就任し、今までとは違うオマーン代表を作り上げていく中で、日本に対してどのような戦いをしようかということは考えていたはずだ。
もちろんコンディション調整もバッチリだ。最終的に日本へ移動するということはあっても、チームとして1カ月活動していれば、良い状態なのは明らかだ。
一方で、日本は8月30日に始動。試合までは3日しかなく、大半の選手が長距離の移動後すぐの試合となった。
しかし「海外組が多くなる中、選手たちが覚悟を持って、短い準備期間の中でも、1戦1戦勝利に向けて準備してくれ、前進してきていた」と森保監督は語り、その点を言い訳にはしないと語った。
吉田も「相手のコンディションがむちゃくちゃ良かったのがある」と相手の状態が良かったことを認めたが「それは言い訳にできない」と語った。
オマーンは、暑熱対策もしていただろうが、試合日はまさかの雨。気温も上がらない中で、オマーン人にとって馴染みのない大雨の試合。しかし、イバンコビッチ監督は「大問題だった」としながらも、「雨に合わせて戦術を微調整して日本のゴールを狙おうとした」とチームの戦い方に微調整を行ったことを明かした。
◆大きな課題となる柔軟性のなさ
試合展開を見ても、日本が劣っていたことは間違いない。もちろん、コンディション面の差も影響し、ピッチ状態の悪さも影響しただろう。しかし、何よりも柔軟性とクリエイティビティが欠けていたように思えてならない。
オマーンの印象として中央を固めて守備をしてくるというスカウティングはあったはずだ。そしてその通り、オマーンは中央をかなり手厚く固め、FW大迫勇也、MF鎌田大地の中央の縦のラインを完全に潰しに行っていた。
2次予選の生命線とも言えた部分が使えなくなった日本。鎌田も大迫もポジションを変えてボールを受けに動いたが、オマーンはポジションを離れた2人に対しては、マークの強度はそこまで高めないものの、しっかりとボールを奪いにいくという約束事は守っていた。
そのオマーンに対し、日本はサイドから崩しにかかる。森保監督は「相手の守備網を崩せるように横から楔を入れていく、縦パスを入れていくということは、これまでやって来たことを出しながら試合を進めて行こうと戦いました」と語っていたが、あまり効果的にプレーしたようには見えなかった。
1つは右サイドの縦の関係だ。これまでは酒井宏樹と伊東純也で良いコンビネーションを見せていたが、この試合ではなかなか酒井が高い位置を取り続けるということができなかった。また、鎌田が受けに近づいたときにも、連動性が低く、仮に抜け出した場合でも、中央に大迫が1人で待っているだけの状態が続き、簡単にクロスを上げる選択ができなかったはずだ。
中央を固められ、サイドからもそこまで効果的に崩せていなかった日本。その中で唯一と言っても良い決定機は、吉田のロングフィードに伊東が抜け出してパスを受けたシーンだった。
ボールを繋いでくるという予想のもとに守っていたオマーンにとって、一瞬の隙をついたロングボールに対しては対応しきれなかった。伊東のシュートは結果としてGKの正面を突いたが、オマーンとしては一番ヒヤリとした場面だったのではないだろうか。
しかし、そのような動きを見せたのはこの時ぐらい。殆どはサイドに展開してクロスというシーンに終始した。
試合前には「行き詰まったときに打開策を見つけたりすることは課題」と吉田が語っていたが、まさにその課題が初戦から出てしまった。
◆打開策はいくらでもあった
では具体的な策は何ができたのか。まず第一に、日本はグループで1番警戒される相手ということ。さらに、日本の情報は収集しやすいということだ。
選手個々の特徴はもちろんのこと、チームとしての戦い方も東京五輪を含め、親善試合を見ていればある程度ポイントを掴むことは簡単だ。それが中央を徹底的に使わせないという判断に至ったとも言えるだろう。
その中で、日本はこれまで通りの戦い方を行おうとした。警戒されることを予測しながらも、手を打つことはなく、いつも通りの入りを見せ、いつも通りの戦い方を選んだ。
もちろん、自分たちのスタイルを通すということも強者になる上では必要なこと。その選択は間違っていたとは思わない。しかし、日本は柔軟性も持ち合わせているメンバーがいるにも関わらず、それを後半の手として打てなかったことは課題だろう。
森保監督は最初の手として2列目の左に古橋亨梧を入れ、原口元気を下げた。右サイドに比べて停滞感のあった左サイドに手を打ちたかったのかもしれないが、それでは何も変わらない。選手の特徴は違えど、戦い方は結局中央とのコンビネーションで崩すということ。オマーンとしては警戒する部分に変化は生まれないのだ。
また古橋も得意のスピードを生かせるシーンが少なく、スペースを使ったプレーは少なかった。チームとして特徴を生かすという点でも、古橋が自ら要求するという点でも、物足りなさはあった。
例えば、前半の戦い方を受けてシステム変更という手も打てただろう。オマーンは攻撃時には3トップ気味になる[4-4-2]のシステムだったが、鎌田と大迫に対してCBとボランチの4枚でケアしにきた。その点では、[4-2-3-1]のシステムにこだわる必要はなかったと言えるる。
試合後に遠藤航も「シンプルにシステムを変えてみても良い」と口にしていたが、例えば[4-3-3]や[3-1-4-2]のシステムでも良いだろう。今の日本代表ならば、メンバーを交代せずともシステムは変えられる。
[4-3-3]であれば、遠藤をアンカーに柴崎岳と鎌田がインサイドに入っても良い。[3-1-4-2]というシステムも酒井宏樹を3バックの一角として起用し、遠藤がアンカーに。長友佑都と伊東がワイドに入り、柴崎と鎌田がインサイドに、大迫と原口の2トップでも良いし、古橋を入れて2トップでも良かっただろう。選手を入れ替えずとも、システム変更で戦い方を変えられたが、最後までシステムは変えなかった。
その他にも後半には東京五輪で良いコンビネーションを見せていた堂安律と久保建英を起用。2人は何度か東京五輪でも見せたコンビネーションで狭い局面を崩し、ボックス内に侵入していた。短い時間で何度か良いシーンを作っていたところを見れば、もう少し長く見たかったというのもある。また、ファウルを得ることもできていただけに、近い距離でプレーできる選手を並べる手もあったはずだ。
この試合では距離感もイマイチで割と分断されるケースが多く、日本が得意とする細かいパス交換で局面を打開することは難しかった。かといって、裏を積極的に摂るということもなく、ケアをされ続ける大迫に当てるという戦い方しかチョイスできなかった。
ピッチ上の判断も重要だが、指揮官としてのメッセージも足りなかったとも言える。南野拓実が起用できない状況で、攻撃のカードが少なかったこともあるかもしれないが、招集時に後ろの選手が多いことも気になる部分ではあった。攻撃のカードを手札として持てていないことも含め、最終予選というものを初めて戦う森保監督にとっては越えなければいけない壁とも言える。
東京五輪ではスペイン、メキシコと実力のある国を前に勝つことができなかった。その悔しさを選手が最も痛感しており、東京五輪世代の選手の奮起も期待したいところだが、監督としても上のレベルに通用できなかったことをこの最終予選にいかしてもらいたいところ。次の中国戦でどう対応力を見せるのかに注目だ。
《超ワールドサッカー編集部・菅野剛史》
W杯本大会への切符は各グループ2枚。上位2カ国に与えられ、3位チームは4次予選と大陸間プレーオフを勝ち抜かなければ本大会には出場できない。
2016年9月1日。日本代表はロシアW杯アジア最終予選の初戦で、UAE代表に埼玉スタジアム2002で1-2で敗れた。
この悪夢を忘れた者はいなかったはずだが、5年後に再び同じ事態に。心のどこか片隅で恐れていた結果となってしまった。
◆明らかなコンディションの差
日本が敗れた要因は多くあるだろう。森保一監督、キャプテンの吉田麻也も試合後に口にした通り、「言い訳にはしない」と語ったが、事実としてコンディションには大きな差があったことは否めない。
オマーンはこの日本戦に向けて1カ月に渡り、セルビアで合宿を敢行。チームとしての成熟度、コンビネーション、そして日本への対策は万全だった。
ブランコ・イバンコビッチ監督が就任し、今までとは違うオマーン代表を作り上げていく中で、日本に対してどのような戦いをしようかということは考えていたはずだ。
もちろんコンディション調整もバッチリだ。最終的に日本へ移動するということはあっても、チームとして1カ月活動していれば、良い状態なのは明らかだ。
一方で、日本は8月30日に始動。試合までは3日しかなく、大半の選手が長距離の移動後すぐの試合となった。
しかし「海外組が多くなる中、選手たちが覚悟を持って、短い準備期間の中でも、1戦1戦勝利に向けて準備してくれ、前進してきていた」と森保監督は語り、その点を言い訳にはしないと語った。
吉田も「相手のコンディションがむちゃくちゃ良かったのがある」と相手の状態が良かったことを認めたが「それは言い訳にできない」と語った。
オマーンは、暑熱対策もしていただろうが、試合日はまさかの雨。気温も上がらない中で、オマーン人にとって馴染みのない大雨の試合。しかし、イバンコビッチ監督は「大問題だった」としながらも、「雨に合わせて戦術を微調整して日本のゴールを狙おうとした」とチームの戦い方に微調整を行ったことを明かした。
◆大きな課題となる柔軟性のなさ
試合展開を見ても、日本が劣っていたことは間違いない。もちろん、コンディション面の差も影響し、ピッチ状態の悪さも影響しただろう。しかし、何よりも柔軟性とクリエイティビティが欠けていたように思えてならない。
オマーンの印象として中央を固めて守備をしてくるというスカウティングはあったはずだ。そしてその通り、オマーンは中央をかなり手厚く固め、FW大迫勇也、MF鎌田大地の中央の縦のラインを完全に潰しに行っていた。
2次予選の生命線とも言えた部分が使えなくなった日本。鎌田も大迫もポジションを変えてボールを受けに動いたが、オマーンはポジションを離れた2人に対しては、マークの強度はそこまで高めないものの、しっかりとボールを奪いにいくという約束事は守っていた。
そのオマーンに対し、日本はサイドから崩しにかかる。森保監督は「相手の守備網を崩せるように横から楔を入れていく、縦パスを入れていくということは、これまでやって来たことを出しながら試合を進めて行こうと戦いました」と語っていたが、あまり効果的にプレーしたようには見えなかった。
1つは右サイドの縦の関係だ。これまでは酒井宏樹と伊東純也で良いコンビネーションを見せていたが、この試合ではなかなか酒井が高い位置を取り続けるということができなかった。また、鎌田が受けに近づいたときにも、連動性が低く、仮に抜け出した場合でも、中央に大迫が1人で待っているだけの状態が続き、簡単にクロスを上げる選択ができなかったはずだ。
中央を固められ、サイドからもそこまで効果的に崩せていなかった日本。その中で唯一と言っても良い決定機は、吉田のロングフィードに伊東が抜け出してパスを受けたシーンだった。
ボールを繋いでくるという予想のもとに守っていたオマーンにとって、一瞬の隙をついたロングボールに対しては対応しきれなかった。伊東のシュートは結果としてGKの正面を突いたが、オマーンとしては一番ヒヤリとした場面だったのではないだろうか。
しかし、そのような動きを見せたのはこの時ぐらい。殆どはサイドに展開してクロスというシーンに終始した。
試合前には「行き詰まったときに打開策を見つけたりすることは課題」と吉田が語っていたが、まさにその課題が初戦から出てしまった。
◆打開策はいくらでもあった
では具体的な策は何ができたのか。まず第一に、日本はグループで1番警戒される相手ということ。さらに、日本の情報は収集しやすいということだ。
選手個々の特徴はもちろんのこと、チームとしての戦い方も東京五輪を含め、親善試合を見ていればある程度ポイントを掴むことは簡単だ。それが中央を徹底的に使わせないという判断に至ったとも言えるだろう。
その中で、日本はこれまで通りの戦い方を行おうとした。警戒されることを予測しながらも、手を打つことはなく、いつも通りの入りを見せ、いつも通りの戦い方を選んだ。
もちろん、自分たちのスタイルを通すということも強者になる上では必要なこと。その選択は間違っていたとは思わない。しかし、日本は柔軟性も持ち合わせているメンバーがいるにも関わらず、それを後半の手として打てなかったことは課題だろう。
森保監督は最初の手として2列目の左に古橋亨梧を入れ、原口元気を下げた。右サイドに比べて停滞感のあった左サイドに手を打ちたかったのかもしれないが、それでは何も変わらない。選手の特徴は違えど、戦い方は結局中央とのコンビネーションで崩すということ。オマーンとしては警戒する部分に変化は生まれないのだ。
また古橋も得意のスピードを生かせるシーンが少なく、スペースを使ったプレーは少なかった。チームとして特徴を生かすという点でも、古橋が自ら要求するという点でも、物足りなさはあった。
例えば、前半の戦い方を受けてシステム変更という手も打てただろう。オマーンは攻撃時には3トップ気味になる[4-4-2]のシステムだったが、鎌田と大迫に対してCBとボランチの4枚でケアしにきた。その点では、[4-2-3-1]のシステムにこだわる必要はなかったと言えるる。
試合後に遠藤航も「シンプルにシステムを変えてみても良い」と口にしていたが、例えば[4-3-3]や[3-1-4-2]のシステムでも良いだろう。今の日本代表ならば、メンバーを交代せずともシステムは変えられる。
[4-3-3]であれば、遠藤をアンカーに柴崎岳と鎌田がインサイドに入っても良い。[3-1-4-2]というシステムも酒井宏樹を3バックの一角として起用し、遠藤がアンカーに。長友佑都と伊東がワイドに入り、柴崎と鎌田がインサイドに、大迫と原口の2トップでも良いし、古橋を入れて2トップでも良かっただろう。選手を入れ替えずとも、システム変更で戦い方を変えられたが、最後までシステムは変えなかった。
その他にも後半には東京五輪で良いコンビネーションを見せていた堂安律と久保建英を起用。2人は何度か東京五輪でも見せたコンビネーションで狭い局面を崩し、ボックス内に侵入していた。短い時間で何度か良いシーンを作っていたところを見れば、もう少し長く見たかったというのもある。また、ファウルを得ることもできていただけに、近い距離でプレーできる選手を並べる手もあったはずだ。
この試合では距離感もイマイチで割と分断されるケースが多く、日本が得意とする細かいパス交換で局面を打開することは難しかった。かといって、裏を積極的に摂るということもなく、ケアをされ続ける大迫に当てるという戦い方しかチョイスできなかった。
ピッチ上の判断も重要だが、指揮官としてのメッセージも足りなかったとも言える。南野拓実が起用できない状況で、攻撃のカードが少なかったこともあるかもしれないが、招集時に後ろの選手が多いことも気になる部分ではあった。攻撃のカードを手札として持てていないことも含め、最終予選というものを初めて戦う森保監督にとっては越えなければいけない壁とも言える。
東京五輪ではスペイン、メキシコと実力のある国を前に勝つことができなかった。その悔しさを選手が最も痛感しており、東京五輪世代の選手の奮起も期待したいところだが、監督としても上のレベルに通用できなかったことをこの最終予選にいかしてもらいたいところ。次の中国戦でどう対応力を見せるのかに注目だ。
《超ワールドサッカー編集部・菅野剛史》
2021年9月3日(金)6:30
戻る
© livedoor